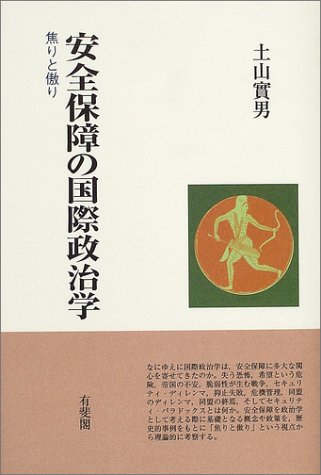本書は、書名の通り、東日本大震災の際に陸上幕僚長の地位にあった火箱もと
陸将が、当時を振り返って書いた著書です。興味深いのは、著者が陸上自衛隊のトップとして、隊員の口内炎を心配するほどの配慮をしながら、同時に隊員に「決死隊」や「特攻」のような危険極まりない命令をだす覚悟をしつつ、部下の命と市民の命をともに守ろうと奮闘している点です。
発災直後の判断
本書は発災の瞬間から始まります。まず驚くのは、著者の判断のものすごい速さです。発災し、エレベーターが動かないので、著者は階段を11階から4階まで駆け下ります。
何をなすべきか。頭の中もフル回転していた。
「生存確率が高い72時間以内に、被災地に大部隊を送り込む。」
「東北方面隊だけでは人数が足りない。五方面隊全てから部隊を集める」
「まずは、東北方面隊を出動させ、直ちに北部・東部・中部・西部方面隊から部隊をだす」
4〜5分後、4階の執務室に着いた時には、運用作戦の骨格は頭の中で完成していた。
(28p)
駆け下りる間に、災害派遣の基本的な構想が頭の中で完成させています。
その後、著者は日本各地の方面隊の司令官に電話をかけて東北への増援指示を伝えるのですが、その際、真っ先に電話した先は、東北に近い北海道ではなく、九州・沖縄の西部方面隊です。「当たり前の話だが、被災地から遠いほど現地到達に時間がかかるから」とのことです。未曾有の震災があった直後、当たり前のように手際よく行動が取れるのはすごいものだと思いました。
こうして陸上自衛隊は全国から東北に駆けつける態勢を速やかにとりました。
被災者に自分の食事を差し出す隊員を注意
興味深く思ったのは、次に著者がすぐ「兵站」に手をつけていることです。
当初、被災地では乾パンのような災害非常食しかありませんでした。
「どうぞこれを食べてください」と、自分の食事を被災者に差し出す隊員も数多くいた。部隊の管理者としては「それはいかん。しっかり戦ってもらうためには、十分に栄養補給しなくてはならない。被災者へのそうした個別の行為は慎むように」と注意せざるを得なかったが(中略)
隊員たちの気持ちは痛いほどわかるが、こんな状態が続いていたら隊員の健康に問題が起きる。その結果、十分な救助活動ができなくなるかもしれないことを恐れた。(p68−69)
自衛隊員が自分は空腹を我慢して市民に食事を与える、というのは美談ですが、救助活動にはカロリーが必要です。「泥水をすすり、草をかみ」というほどの苦労をして戦った旧日本軍は、戦場でも兵士に牛肉を食べさせていたアメリカ軍に負けました。
経営者は、「頑張れ、一生懸命やれ」と部下を駆り立てることも時には必要ですが、そもそも継続的に頑張れるだけの環境や休養を整えてやることが先決問題です。
「缶詰ばかり食べて、口内炎になった隊員がいる」と言う報告を受けた著者は、ビタミン剤を配布するようにするなど、現場隊員の健康を案じて色々な対処を取っています。
やる気があり過ぎるのも問題
食事だけでなく、メンタル面のケアも必要です。本書にはこうあります。
多くの遺体を収容する作業によるPTSDも心配だった。・・・医師や臨床心理士など専門家の「陸幕メンタルヘルス巡回指導チーム」を現地に派遣して、PTSD等の予防と発症の恐れのある隊員の早期発見に努めさせた。
・・・しかし、対象とされた隊員はいずれも「何でもやります」「やらせてください」と極めて士気は高かった。逆にあまりに士気が高すぎるのも気がかり出会った。発災から約1週間がたったころ、文字通り不眠不休で人命救助に当たっており、明らかに過活動状態出会った。このままにしておくと、隊員がいつかポッキリ折れてしまうのではと懸念した。(p74)
そこで、長期戦を戦えるように、隊員をローテーションで強制的に休ませる「戦力回復センター」を設置したそうです。
残念ながら、そのような処置があっても、災害派遣中に脳溢血などで急死された隊員が3人。災害派遣中は大丈夫でも、任務終了後に自殺してしまった方も何人もいるそうです。そういった被害をなくすためにはさらなる研究が必要でしょう。
とはいえ、こういった食事や休養へ配慮する視点があったことを見ると、陸上自衛隊は太平洋戦争中の日本軍と違い、兵站の重要性を強く感じているようです。
ただ、重要性を感じていたからといって、十分な人員を持っているかといえば、それはまた別の話のようで、本書中にも輸送力の不足の話が多く出てきます。
「使い捨てではない隊員の命」
原発の危機的な状況が判明すると、本書の記述はさらに緊迫の度を増していきます。
3号機の水素爆発で4人の隊員が被曝。ヘリや車両には、放射線を遮るタングステンの板を応急調達して備え付けましたが、問題となったのは被曝量の基準です。
当時の政府の対応はひどい者だった。事故前まで国際放射線防護委員会の勧告に基づいて日本が採用していた放射線量の限度は・・・緊急作業時の上限が年間100ミリシーベルトだった。事故直後には年間200ミリシーベルトに引き上げ、さらに政府からは「500ミリシーベルトでもいいのではないか」との打診があった。
私は即座に「やめていただきたい!」と大臣に申し上げた。限度を引き上げたばかりで、舌の根も乾かないうちにさらに引き上げるという。正直腹が立った。自衛隊員の命をあまりにも軽く見ているのではないか。(p77)
このように、著者は被曝量上限の引き上げに反対して、現場の隊員を守ろうとしています。
その時が来たら、空挺隊員を原子炉の屋上に降下させる。
しかし、部下に優しいだけではありません。無用の危険を避ける一方で、他に手段がない場合は悲壮な作戦をとることも準備しています。
原子炉内にホウ酸を直接投入して放射線を封じ込める作戦です。そのためにはヘリからの投下では不足です。
方法はただ一つ。ヘリからロープで建屋の屋上にたち降り、屋上から横壁に接近し、横壁に開いた穴からホウ酸を投入する。これしかない。決死隊だ。・・・2号機建屋屋上でこれだけの作業をしたら、致死量に近い放射能を浴びることは避けられない。直上で長時間滞留するヘリの操縦士も、ものすごい量の放射能を浴びるだろう。しかしー(p98)
著者は、この作戦に投入できるのは最精鋭の空挺隊員しかないと考え、準備をさせました。実際には地上からの放水で事態が落ち着いたため、隊員を建屋屋上に降下させるこの作戦は構想だけで終わりました。しかしその後も最悪の事態に備え、投入できる隊員の準備だけはなされていたそうです。
万一に備えて待機を続けた空挺隊員に、著者はこう指示したそうです。
「諸君が現在の任務に物足りなさを感じていることは十分理解している。・・・原発は現在小康状態だが、いつ何時最悪な事態になるとも限らない。・・・10km圏内に住民も残っている。職員、住民の救出、原子炉へのホウ酸投入などが必要になってくる場合もある。
私は、その時は諸君に最先頭に立って行動してもらうことを考えている。その時に備えて、個人の被曝線量が限度を超えないように待機していてもらいたい」
山ノ上第一空挺団長、赤羽第二大隊長は「最後は”特攻”もあるのか」「ならば、その時に備えなければ」と得心したようだった。(p141-2)
当時のテレビを思い出すと、原子炉直上をヘリで通過するのさえ、恐ろしく見えたものです。そこに、生身の人間を降下させるとなれば、それを命じる人も、命じられる人も、求められる覚悟は想像を絶するものがあります。
一方で隊員の被曝量や健康を案じながら、他方では最悪の時には隊員の命とほとんど引き換えにして原発を止める計画を準備する。最悪の事態では、そのような究極的な決断があり得たのが、あの時の日本だったのです。
本書には他にも、未曾有の事態に対して、色々な工夫を重ねて矢継ぎ早に対処していく自衛隊の姿が描かれています。色々な点で、非常に興味深く読めた本でした。








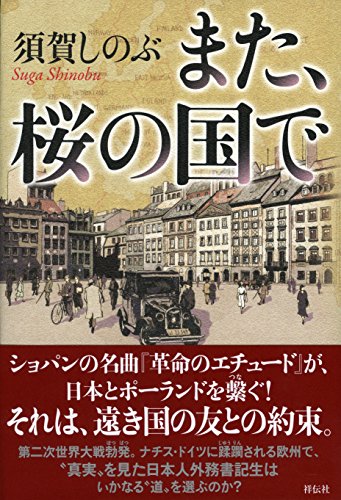








![ダイ・ハード 新生アルティメット・コレクションBOX(「ダイ・ハード」スペシャル・ディスク付) [DVD] ダイ・ハード 新生アルティメット・コレクションBOX(「ダイ・ハード」スペシャル・ディスク付) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DcDL8aCEL.jpg)